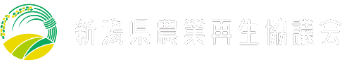水田収益力強化ビジョン
水田収益力強化ビジョンとは
水田収益力強化ビジョンは、地域の特色のある魅力的な産品の産地を創造するための地域の作物生産の設計図となるものです。全国の需給見通しや自らの産地の販売戦略等を踏まえた地域の水田における作物ごとの取組方針・作付予定面積、高収益作物の導入等による収益力強化に向けた取組方針、産地交付金の活用方法等を明らかにし、地域で共有することで、各農業者が主体的に自らの作付計画を判断し、需要に応じた生産を進め、地域の特色ある産地づくりに向けた取組を更に推進することを目的としています。水田収益力強化ビジョンの作成が産地交付金による支援の要件となります。
令和7年度のビジョンはこちらをご参照ください。